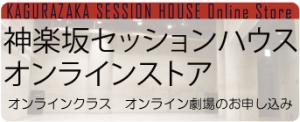Voice of Bando Sengiku
セッションハウスで日本舞踊を指導している坂東扇菊がダンスの境界を越えて、日本舞踊やバレエ、コンテンポラリーのダンサー達15人がそれぞれの持ち味を生かして登場する舞台を創り出し、高い評価を得る公演となりました。
日本舞踊の越境旅 坂東扇菊
日本舞踊の越境旅 坂東扇菊 多ジャンルのダンスの融合する坂東扇菊版『蝶々夫人』プロジェクトは、セッションハウス企画室主催の「ダンスブリッジ」公演の一環として行われました。初めての方と創りたいという意思を”架ける橋”とするダンスブリッジは、3回にわたる「オーディションワークショップ」から始まり、延べ人数30人を超えるダンサーの参加を得て開始されました。
その先行作となった、歌劇 蝶々夫人より『蝶々夫人』は、2023年6月国立小劇場で初演されました。この物語は明治時代の長崎を舞台に実話を元にしています。原作はアメリカ人のロングが小 説として発表、それを元にイタリア人のプッチーニがオペラとして作曲しました。様々な国の巨匠 たちが挑んできた「Madam butterfly」。ここに日本にしかない魅力が潜んでいるのかも知れませ ん。欧米列強国を相手に、開港したばかりの港には、きっと、蝶々さんのような人は何人も居た のでしょう。1904年にミラノのスカラ座で初演されてから、120年の時を経て、時代の狭間に揺 れた蝶々さんのうぶな心を、再び、この現代へ甦らせたいと願い、作品創りに挑みました。
絹の着物から襦袢に至るまで、立ち振る舞いから目線の落としどころまで、全てのことに気を 配りながら、リハーサルが行われました。また、それらと並行して心意的な面にも触れていきまし た。「伝統芸における芸術的可能性とは」、踊りを通して今日の社会でどのような創造的な生き方が可能なのか、本来、表現芸術とは人間を自由にするために学び、個人の力を拡張し、真に自由な人として挑み続けることでしょう。
セッションハウスでの公演にあたり、まず、演出面で、このスタジオ空間と「和」の要素をどのように融合させられるか、また、着物の動きをこの場所でどのように美しく魅せられるかなど、考えを巡らせました。そこで、客席とステージを従来の使い方ではなく、横長に使うことにしました。それにより、場所によって見え方が変化し、前景と後景に絵画のような印象を持たせることができたようです。横長のステージ効果としては、着物で動く流れを創り出すことができ、また、畳や障子を効果的に配置し、「和」の雰囲気を醸し出す工夫を試みました。
この舞台には、様々なジャンルの蝶々夫人が登場します。そして、一人の蝶々夫人の4つの心情の視覚化を試みました。複数の兵士や芸者、蝶々夫人を取り巻く様々な人々により、時代背景を増幅させ、なぜか懐かしい明治という時代の一片を彷彿させるように、人物を配置しました。また、時間のながれのなかで変容する人間の心理に焦点をあて、それを「仕草」という日本舞踊の特質でみせていくところに主眼をおきました。そして、舞踊と演劇が融合したダンスシアターであることを目指しました。 「百の言葉より、一つの仕草が心を打つときがある。」 私は、言葉では伝えきれない感情を、体で表現することは、どのジャンルも同じことだと確信し、感情の視覚化を第一に、作品を創りました。
日本舞踊の越境旅として、「ダンスブリッジ」公演の一環を担った、坂東扇菊版『蝶々夫人』 は、ダンスカンパニーコンドルズのメンバーや、マドモアゼルシネマのダンサーが加わり、さら に越境感が高まりました。 2日間、3回の公演チケットは完売、キャンセル待ちという反響の中、みなさまのお陰で無事に幕を下ろすことができました。web配信もされましたが、その後の反響はまだまだ収まらず、日本舞踊社の月刊誌『日本舞踊』に「蝶々夫人」の舞台写真や記事が掲載されました。また、『国際演劇年鑑2025』への掲載や、『ブリタニカ国際年鑑2025年版』書籍及び同書籍『電子版ブリタニカ』に、2024年の国内外の重要な公演の一つに選ばれ、掲載される運びとなりました。 日本舞踊の越境旅は、まだまだ終わりなき旅になりそうです。
坂東扇菊
ヴォイス・オブ・セッションハウス2024より抜粋