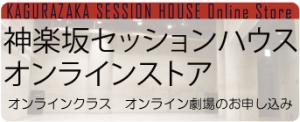Voice of Ishibuchi Satoshi
2024年の最後の公演となった「ダンスブリッジ・トーキョーの阿国」で音楽隊を担った石渕聡が、ダンスとの協業の成果とその意義を分析した一文を寄稿してくれました。
「トーキョーの阿国」におけるダンスと音楽の協業大東文化大学教授 石渕聡
12月に行われた『トーキョーの阿国』(振付・演出:伊藤直子)は、そのクリエイションの段階から、何か日本のどこかの地域のお祭りのような得体の知れないエネルギーを呈していた。キャストはお馴染みのマドモアゼルシネマのレギュラーメンバーを中心に笠井瑞丈、望月崇博の男性2人、20代の若手女性ダンサーを加え総勢9名。そして音楽隊がプロのチンドン屋アーティストの栗原モナコと石渕の2人という構成であった。
私がここで述べたいことは、リハーサル現場で、振付けと共に作曲され、シーンがまとまっていく様子が、あまりにも楽しく、豊かな時間であったこと。たとえば音楽家がシーンをみて、数日後にそれに合う音楽を作ってきて、改めて合わせてシーンをまとめ上げていくような方法(おそらくはこちらの方が、音楽的には制作時間がかけられている分、隙のない音ができることも事実である)と違って、全てがダンスのリハーサル現場で「今・ここ」で生まれてくるという、何やら「とんでもなくダンスと音楽の根っこが同じ感覚」を持てたことを言語化しておきたい。
そもそも、地域の祭りのお囃子の座(今でも子ども達に太鼓、笛や舞を地域活動として教えてそれを年越しや祭りなどで奉納している)では、踊る人と演奏する人が画然と分かれていないことはよくあることである。先日ちょうど地域のお囃子座の方から、子ども達ははじめに太鼓と同時に舞を習って、太鼓が出来るようになって、年齢が少し高くなると篠笛を始めると伺った。教えている大人は、太鼓も舞も笛も全て舞台上で入れ替わり行っているのである。つまり、この場合ダンスと音楽は分業されていないのだ。
この度、「阿国」という題材がそれを呼び寄せたのか、振付け演出の伊藤直子の誘導であったかの真実は闇の中であるが、音とダンスが共に生まれる奇跡の連続があまりにも自然に行われていた。音楽隊はモナコと石渕は以前から馴染みがあったので、タッグ自体は全く問題なく入ったが、果たして何シーンぐらい演奏するのか、何の楽器を演奏するのかという情報がなくて、「何やら和的な題材らしいので使える楽器を持ち寄ろうか」というノリで、楽器を持ち寄って音遊びが始まった。持ち寄った楽器でモナコが演奏するものは、アルトサックス、三味線、チンドン太鼓、パーカッション小物、アコーデオン、歌、サズ(トルコギター)、石渕が演奏するのは、篠笛、三味線、マンドリン、ささら、アコーデオン、二胡、歌などである。伊藤は今回は意図的に複数の楽器を演奏できる二人を集めて、シーンによって、奏でる音を変えてほしいかったらしいことは、作品を進める中で伺った。
例えば、竹之下たまみと笠井瑞丈のデュオシーンを作っている中で、我々がアコーデオンとアルトサックスの音色を当てると、その瞬間、シーンが動き出すのである。もちろん、我々が踊るわけではないし、ダンサー達も演奏するわけではない。そうではなくて、ダンサーが音楽を奏でさせ、楽隊が二人を踊らせる。そこには、分業というようなそっけない無味乾燥な作業的段取りは微塵もなく「出会いの爆発」が出現するのである。
振り返ってみると、このような奇跡を迎えることができる条件は、複数指摘できる。一つは、伊藤の振付・演出が、全て「無音」の中で行われていたことは大きな要因である。というのは、振付家やダンサー達は「暫定的な仮の曲」で、シーンを作り進めると「その曲のイメージ」が先行してしまうというのはよくあることである。伊藤はそのことを熟知していて、演奏シーンに関しては、一切既製曲を使わないで「無音の中で粛々」と(粛々というよりも超盛り上がってだと思うが)作っていたのである。もう一つは、無音で作られたシーンに楽隊が現場で曲を当てる時に、音楽隊はキャストのイメージ、前後のシーンの雰囲気等から楽器を選択し、「それでは始めましょう!」の合図で、ダンサーの動きを見ながらの「即興演奏」で演者に音楽を委ねるのである。
時には動きに同調して「高まったり静まったり」、逆に「動きを際立たせる」ために音楽は「静」に徹したり、あるいはそのような計算も何処かにいってしまい「ただただ惹き込まれて」演奏したり、何度か合わせていくと即興だったものが「自然と形を得て」、まさに腑に落ちてくるのである。それはおそらくはダンサー側にも同じような変容が起こっていることは想像に難くない。
伊藤がこの作品で目論んだことは、阿国という個人(あるいは集団的個人)の生き様の精神的中核をトレースすることで、我々演じ手の人間的な部分、つまり、踊る人形としてのダンサーではなくて、恋、名誉、欲望などでメチャクチャにマミレテイル「肉を纏ったダンサー」をそれぞれ9名分、舞台に現出させることであったろう。それが、アッと驚く為五郎で、それだけにとどまらず、彼女(伊藤)はこの作品において、ダンスと音楽の分業的な垣根を取り払い、ダンス芸術が古来から本来的に持っている本質である「ダンスと音楽が未文化な場」を召喚してしまったのだ。
石渕聡
ヴォイス・オブ・セッションハウス2024より抜粋