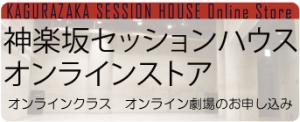Voice of Watanabe Ichie
2011年3月11日に東日本を襲った大震災と福島原発の事故の1年後から作家の渡辺一枝さんが開いてきたトークの会「福島の声を聞こう」は昨年も3回開催されましたが、今もなお帰還困難区域があるように放射能汚染の恐れが続いています。その会を主宰している渡辺一枝さんの声をお聞き下さい。
『原発事故から14年、福島の今』 渡辺一枝
2011年3月に東京電力福島第一発電所が爆発事故を起こしてから、14年が経つ。当初は節電と称して店舗や企業のネオンサインが消え、営業時間が短縮されて、東京の夜は暗く静かだった。が、それもごく短い間だった。それでも巷には反原発・脱原発の声が溢れて、各地で集会が持たれていた。
セッションハウス・ガーデンで「渡辺一枝トークの会 福島の声を聞こう!」第1回を催したのもそうした流れの中での、2012年3月7日だった。これは2011年8月から福島に通い始めた私が、現地の状況を伝えたいので当事者から直接話を聞く会を持ちたいと、セッションハウス企画室の伊藤孝さんに相談して叶ったことだった。あれから回を重ねて、今年2月22日には48回目を迎える。最初の頃は毎回100名近くの参加者を数えたが、最近は30名前後となっている。
新聞やテレビなどメディアが伝える福島のその後は、「復興」した現地の様子を伝える記事が多く、今もまだ数万の避難者がいることも、福島県(東京都や大阪市も)が、避難者を「追い出し裁判」にかけていることを伝えてはいない。
「安心・安全」と言って国策で作ってきた原発が事故を起こしたら、今度は事故のことは早く忘れさせよう、無かったことにしようとしているように思える。
なるほど、現地に行ってみれば常磐線の駅舎は、双葉・大野・夜ノ森・冨岡、いずれも新たに建て替えられ駅周辺は再開発予定地として大型車両が行き交っている。浪江駅周辺もこれから大々的に再開発が行われていく。隈研吾デザインで駅舎と一体になった駅前の街づくりだそうだ。
原発事故で避難指示対象となった福島県浜通りの市町村は、帰還困難区域を除いて避難指示が解除になったが、汚染は残り安心して暮らせる状況には戻らない。帰還を諦めた住民たちは、引き裂かれる思いで先祖伝来の家屋解体の申請をした。更地が増え事故前よりも大幅に人口減少したこれらの地域では、「移住セミナー」などと称して、移住対策が進められている。「復興フロンティア」と謳ったところもあったが、私はその言葉に北米大陸の「西部開拓史」を思い浮かべた。移住対策として、住宅購入のための補助金200万?500万円の補助、また起業支援金として経費補助が最大で400万円の補助がある。メディアが伝えるその後の福島は、こうして起業した企業や組織を華々しく取り上げる。
若い世代が移住するには子育てに関しても手当が必要であり、学校再建はいち早く取り組まれ、認定こども園と小中一貫校のセットで建設されてきた。それらの新設校は、例えば有名デザイナーによる制服が無償で貸与されたり、校歌が有名詩人作だったりする。修学旅行の積立金は保護者負担無し、学用品も無償というように優遇措置が取られている。だから住民票は元の居住地に残したまま避難先で暮らす住民が、子弟を新設された学校へ通わせる例も少なくない。その場合は、避難先から通学バスでの送迎がある。被ばくに関してなんの情報も出さないまま移住を勧める国の姿勢に私は、かつての満州開拓の歴史が脳裏に浮かぶ。
これも大きく喧伝されたが、双葉町には2020年9月に「東日本大震災・原子力災害伝承館」が開館した。これは災害実態を伝え伝承していくことよりも、復興のプロジェクト(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル・農林水産業、医療関連、航空宇宙)である「福島イノベーションコースト構想」について説明・宣伝する施設だ。その司令塔とも目されるのが浪江町に建設される「福島国際研究教育機構(エフレイ)」で、これはアメリカの「パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)」と覚書を結び連携していく施設だ。
PNNLは、長崎に投下された原爆のプルトニウムを作ったハンフォードの核施設に近いリッチランドに在り、国家安全保障に重点を置く対策を開発している施設だ。つまり軍事研究施設で、またそれと併せて「米国の原子力産業を世界的に競争できるように強化する」施設でもある。つまり、福島イノベーションコースト構想が掲げるのはどれも、軍事に転用可能な国家プロジェクトで、さらに原発推進構想なのだ。
このような国の復興計画を、地元住民で浪江町から二本松に避難しているHさんは、「私たちが当初思い描いていた町は、これまで住んでいた町民同士の温かい繋がりの中で、文化を育み生活が続いていく町でした。国が進める大きなプロジェクトによって私たちの町は景色も人の心も前とは似ても似つかない地域になっていくような気がしてなりません」と言っている。これはHさんだけではなく、大多数の地元住民の思いなのだ。
旅行会社が「ホープツーリズム」などと称しての福島現地を訪ねるツアー企画があるが、「福島の復興」を印象付けるべく新たに造られた学校や役場、起業された商業施設などが見学コースとなっている。もしあなたが現実の福島を見たいなら、政府に忖度するこのようなツアーではなく、私が企画している「被災地ツアー」に参加してほしい。
福島だけではなく東北地方は、食糧、労働力、エネルギーなど様々を供給してこの国の経済的繁栄に寄与してきた。だが、「白河以北一山三文」の言葉は未だ死語になっていない。私にはこれが「植民地思想」に思えてならない。
渡辺一枝
ヴォイス・オブ・セッションハウス2024より抜粋